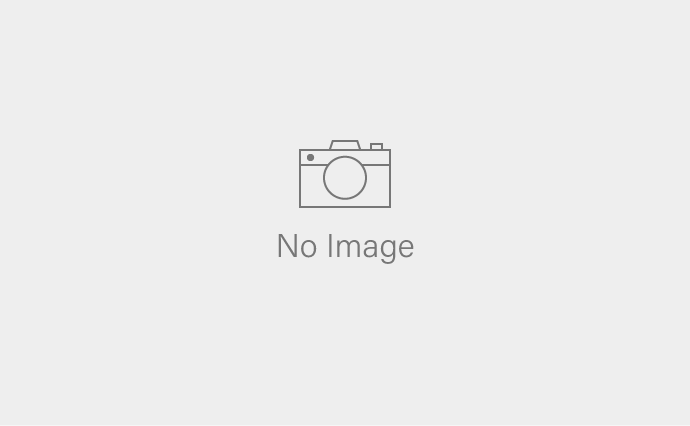こんにちは、kentaroです。
今回は、中国の気候と地域ごとの特徴について紹介していきます。
私自身も中国留学中に数多くの旅行先に遊びに行った経験があるのでそれも踏まえて説明していきます。
中国は南北に長く、地域ごとにまったく違う表情を見せます。
北では真冬に息が凍る一方、南では一年中半袖で過ごせる――。
まさに「季節の博物館」のような国です。
この記事では、中国を6つの地域に分けて、
それぞれの気候の特徴・旅行のベストシーズン・注意点を、僕自身の体験とあわせて紹介していきます。
中国の大体の気候区分
まずは中国のおおよその気候区分について説明していこうと思います。
出典:Wikipedia Commons「中国のケッペン気候区分図」rel=”noopener”図からもわかるように中国には様々な気候区分が存在しています。
東部・南部(沿岸部): 緑色で示される温暖湿潤気候(Cfa)や温暖冬季少雨気候(Cwa)が広がっています。この地域は夏のモンスーン(季節風)の影響を強く受け、高温多湿な夏が特徴です。
北東部: 青色系の亜寒帯気候(冷帯)が分布しており、冬はシベリア高気圧の影響で非常に寒冷になります。 西部・内陸部: 赤色系の砂漠気候(BWk)や黄色系のステップ気候(BSk)といった乾燥気候が広範囲を占めています。タクラマカン砂漠やゴビ砂漠などが含まれ、海から遠く離れているため降水量が極端に少ないことが特徴です。
南西部: 紫色で示されるチベット高原一帯は、標高が非常に高いため、ツンドラ気候(ET)や氷雪気候(EF)といった高山気候(寒帯)となっています。
このように、中国は南の温暖な地域から北の寒冷な地域、東の湿潤な地域から西の乾燥した砂漠地帯まで、一つの国の中にほぼ全ての主要な気候タイプが存在していることが視覚的に理解できますね。
また、降水量の違いについてもこちらで確認することができます

地域によって降水量にも大きな差があります。南部の沿岸部では年間を通して雨が多いのに対し、西部や北部では非常に乾燥しています。
① 東北部(黒龍江・吉林・遼寧)
極寒の世界と短い夏——ハルビンで体験した氷点下27℃の冬
僕がハルビンを訪れたのは1月。
気温はなんとマイナス27℃。
ここまでくると水というすべての水が凍っています。川・湖・吐く息や涙のすべてが凍っていました。
地元の人に聞くと、「今年はまだ暖かい方だよ」と笑われたのを覚えています。
実際、吐く息がその場で凍るような感覚で、映像でよく見る“タオルが一瞬で凍る”現象も自分でできました。

この写真は哈尔滨(ハルビン)の冰雪大世界のもので太陽が昇っている間でも氷が溶けることがないのでこうして期間限定のテーマパークも作られています。
それでも街には人が溢れ、夜は氷雪祭りのライトアップでまるで別世界。
寒さを忘れるほどの美しさでした。
夏は短く、空気が澄んでいて快適。
東北料理がこってりしているのも、寒冷な気候で体を温めるための知恵から来ています。
② 華北地方(北京・天津・河北)
乾燥と黄砂の季節、そして秋の青空
北京の気候はまさに「乾燥の都」。
北京を中心とする華北地方は、四季の変化がはっきりしています。
冬は寒く乾燥し、春は黄砂が舞う季節。
「春風に砂を感じる」と言われるのもこの地域ならではです。
特に冬から春にかけては空気が非常に乾きます。
そして春先になると、モンゴル高原から黄砂や砂の粒子が飛んでくることも。
僕が北京で話を聞いた地元の人も、「最近は大気汚染がひどい日がある」と言っていました。
確かに10月頃でも、日によっては空が少し霞んで見えることがあります。

この写真は国慶節中(10月初め頃)の北京市内の街並みです。きれいではあるんですけれど空気はよどんだ感じがしますよね。
この時期は空気中に粉じんや有害成分が舞っていますので注意が必要です。私は当時この大気汚染マップを毎日チェックしていました。
ただし、秋の澄み切った空と、天安門広場に沈む夕日は本当に見事。
個人的には、北京を訪れるなら10月中旬~11月初旬が一番おすすめです。
③ 華中地方(上海・江蘇・浙江)
梅雨と蒸し暑さ、そして春の短さを実感する街
長江流域の華中地方は、亜熱帯モンスーン気候に属し、湿度が高く雨の多い地域です。
上海を訪れたとき、一番驚いたのは春の短さでした。
4月の終わり頃には、すでに30℃を超えていました。
「え、もう夏?」と思うほどの気温で、街中では半袖の人も多く見かけました。特に北京という緯度が少し高い地域に住んでいたから余計にそれを感じました。

6月頃からは長い雨期に入り、「メイユー(梅雨)」と呼ばれる湿気の多い季節がやってきます。
外を歩くと、空気そのものが重たく感じるような湿気。
傘が手放せない時期でもあります。
でも、その分だけ秋の空気が澄み、杭州や蘇州の風景が一層美しく見えるのです。
できるだけ重ね着しやすい服を持っていくと昼夜の寒暖差にも対応がしやすいと思います。
④ 華南地方(広東・深圳・香港・海南)
一年中あたたかい南国――ただし台風には要注意!
広東省や深圳、香港などがある華南地方は、一年を通して温暖で湿潤。
1月でも20℃を超える日があり、街には半袖姿の人も。
ただし、6〜9月は台風のシーズンで、激しい風雨に注意が必要です。
実際私が深圳を訪れたときは、まさに台風シーズンの真っ只中でした。
その日、飛行機がすべて欠航になり、12時間延期となりました。

やっととんだ飛行機も着陸の瞬間はバッチリ雨。台風に関係なく夕方はスコールという突発的な大雨が降ることも雨季の間では日常なので折りたたみ傘は必須アイテムだと思います。
外では強風が吹き荒れ、窓ガラスが震えるほどの勢い。
「南国=穏やか」というイメージを一瞬で覆されました。
ただし、普段の気候は非常に温暖で過ごしやすく、冬でも薄い上着で十分。なんなら日中は半そででも生活することができます。
1月でも20℃を超えることが多く、花が咲き、果物が豊富なまさに常春の街です。
⑤ チベット高原(チベット自治区・青海省)

空が近い場所で感じた、昼夜の寒暖差と強い日差し
標高4000m級のチベット高原では、「一日の中に四季がある」といわれるほど、昼夜の温度差が大きいです。
空気が薄く乾燥しており、紫外線が非常に強いのも特徴。
日中は半袖でも夜はダウンが必要になることもあります。
チベットを訪れるとまず感じるのは、「空の青さ」と「空気の薄さ」。
標高が高いせいで日中は日差しがとても強く、じりじりと肌を焼くような感覚があります。
でも夜になると一気に冷え込み、氷点下近くまで気温が下がることも。
過酷ながらも、他にはない「天空の美しさ」がここにはあります。
服装は重ね着が基本で、日焼け止めと帽子は必須です。
⑥ 西域地方(新疆ウイグル自治区・敦煌など)

砂漠と果実の国――極端な気候が生む豊かさ
敦煌やカシュガルを旅したとき、まず驚いたのは昼夜の温度差。
昼は40℃近くあるのに、夜になると一気に涼しくなる。
西部の新疆や敦煌は、典型的な乾燥気候。
夏は40℃を超え、冬は氷点下まで下がるという極端な環境です。
砂漠特有の乾いた風が肌を撫で、夜空には満天の星が広がっていました。
そんな過酷な自然の中でも、トルファンやカシュガルなどのオアシス都市ではブドウやメロンなどの果物が豊富。
「こんな乾いた土地で、どうしてこんなに甘い果物ができるんだろう」と感動しました。
まさに自然の厳しさと恵みが共存する場所です。
まとめ:中国の気候は“生きた地理の教科書”
こうして見ると、中国はまさに“気候の博物館”。
北の氷雪、南の熱帯、西の砂漠、東の湿潤。
すべてがひとつの国の中に共存しています。
旅行や留学、仕事などで訪れるときは、
行き先と季節をしっかり調べて、服装・移動手段・体調管理を準備するのがポイントです。
そして、気候が違えば人の暮らしも違う――
そんな「多様性」を肌で感じられるのが、中国という国の最大の魅力だと思います。