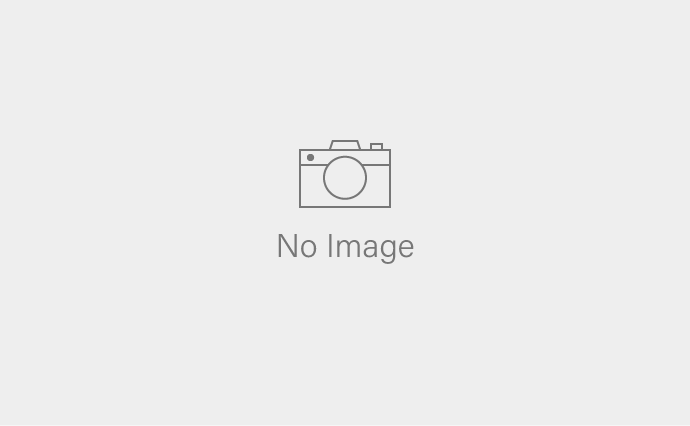こんにちはkentaroです。
お茶といえば「緑茶」「紅茶」「烏龍茶」などが思い浮かびますが、実は中国では発酵度の違いによっ て体系的に分類された「六大茶類」という考え方があります。
これは、世界中のお茶の基本を理解するうえで欠かせない知識です。
この分類を知ることは、中国茶の奥深い世界への第一歩です。
本記事では、六大茶類それぞれの特徴・製法・代表 銘柄を、発酵度を軸に分かりやすく解説します。
六大茶類を分ける「発酵」という鍵
中国茶の分類は、主に茶葉に含まれる酵素(酸化酵素)を働かせるか否か、つまり「発酵(酸化)の程度」によって区別されます。
発酵が進むにつれて、茶葉の色は緑から赤褐色、そして黒へと変化し、味と香りの性質も劇的に変わっていきます。
| 茶類 | 発酵度 | 主な工程 | 色調 | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 緑茶 | 不発酵 | 殺青・乾燥 | 緑 | 西湖龍井 |
| 白茶 | 軽発酵 | 萎凋・乾燥 | 白銀色 | 白毫銀針 |
| 黄茶 | 微発酵 | 殺青・悶黄 | 黄 | 君山銀針 |
| 青茶 | 半発酵 | 萎凋・揺青 | 青緑〜赤褐色 | 鉄観音 |
| 紅茶 | 全発酵 | 揉捻・酸化 | 赤 | 祁門紅茶 |
| 黒茶 | 後発酵 | 渥堆(微生物発酵) | 黒 | 普洱茶 |
1. 緑茶(りょくちゃ / Green Tea):不発酵の清々しさ

発酵度:不発酵
緑茶は、中国の茶葉生産量で最も多い茶類であり、日本で一般的に飲まれている煎茶と同じく「不発酵茶」に分類されます。当然日中どちらでも飲むことができる緑茶ですが、日本での普及率のほうが高いように感じました。中国の料理屋さんなどでは緑茶を注文する機会はあまりなかった気がします。
- 製造のポイント: 摘み取った茶葉をすぐに高温で加熱する「殺青」(さっせい、Shāqīng)という工程で、茶葉内の酸化酵素の働きを止めます。これにより、茶葉が持つ本来の色と成分が保たれます。
- 特徴: 「三緑」(乾いた茶葉の色、茶湯の色、淹れた後の茶葉の色が全て緑色)が特徴。清らかでさわやかな香りを持ち、茶葉本来のフレッシュで若々しい味わいが楽しめます。
- 代表銘柄: 西湖龍井(せいこりゅうせい)、洞庭碧螺春(どうていへきらしゅん)、黄山毛峰(こうざんもうほう)。
2. 白茶(はくちゃ / White Tea):最も自然な製法

発酵度:軽発酵(微発酵)
白茶は、その名の通り、茶葉の表面に生える銀白色の産毛(白毫)を特徴とする、最も自然な製法で作られる希少なお茶です。実際に値段も中国の通販サイトで見たときに明らかに値段が高かったです。白茶1杯分でその他の茶葉10敗分は買える感じでした。
- 製造のポイント: 摘採後の萎凋(自然乾燥)と文火烘乾(低温での乾燥)のみで、殺青や揉捻(揉む工程)をほとんど行いません。製法がシンプルゆえに、茶葉の品質がそのまま味に直結します。
- 特徴: 外観は芽毫が完全で銀色の産毛に覆われ、香りは清らかで新鮮です。茶湯は淡い黄色がかった緑色で透明感があり、味わいは淡泊ながらも清涼感のある甘さが後に残ります。
- 代表銘柄: 白毫銀針(はくごうぎんしん)、白牡丹(はくぼたん)、寿眉(じゅび)。
3. 黄茶(こうちゃ / Yellow Tea):中国固有の希少茶

Geminiにより生成
発酵度:微発酵
黄茶は、中国固有の茶類で、生産量が非常に少なく、希少なお茶です。
緑茶に似た製法に、独自の工程が加わります。
- 製造のポイント: 緑茶と同じく殺青を行った後、まだ温かいうちに布などで茶葉を包み、湿った熱で蒸し、黄変させる「悶黄」(もんおう、Mènhuáng)という工程を経ます。
- 特徴: この悶黄により、茶葉と茶湯が美しい「黄色」に変化します。緑茶と比べて味がよりまろやかで優しく、甘く爽やかな風味と回甘(後から戻る甘さ)が生まれます。
- 代表銘柄: 君山銀針(くんざんぎんしん)、霍山黄芽(かくざんこうが)、蒙頂黄芽(もちょうこうが)。
4. 青茶(せいう/烏龍茶 / Oolong Tea):半発酵が生む多様な香り

Geminiにより生成
発酵度:半発酵
烏龍茶(Wūlóng Chá)は、中国語で「青茶」(Qīng Chá)とも呼ばれます。発酵の程度が非常に幅広く、その多様な香りが最大の魅力です。
- 製造のポイント: 萎凋後、茶葉を軽く揺らして茶葉の縁を少し壊し、酵素の働きを促す「揺青」(ようせい、Zuòqīng)が重要な工程です。この半発酵の度合いをコントロールすることで、緑茶に近い清香から紅茶に近い熟果香まで、様々な香りが生まれます。
- 特徴: 茶葉の縁が赤く、内側が緑色になる「緑葉紅鑲辺」(りょくようこうそうへん)と呼ばれる特徴的な外観を持ちます。緑茶の清らかさと紅茶のまろやかさの両方を兼ね備えた、華やかで奥深い味わいが魅力です。
- 代表銘柄: 凍頂烏龍(とうちょうウーロン)、武夷岩茶(ぶいがんちゃ)、安渓鉄観音(あんけいてっかんのん)。
5. 紅茶(こうちゃ / Red Tea):完全発酵の芳醇さ

Geminiにより生成
発酵度:全発酵
中国語の「紅茶」(Hóng Chá)は、英語圏の「Black Tea」(ブラックティー)に相当します。世界中で愛飲されている紅茶の原点であり、その発祥は福建省の武夷山一帯とされています。実際に私が出演した中国の教育テレビでテーマがお茶の歴史の際武夷山について語られていました。
- 製造のポイント: 揉捻後に茶葉を完全に酸化(発酵)させます。この工程により、茶葉内の成分が大きく変化し、特有の芳醇な香りや甘さが生まれます。
- 特徴: 乾いた茶葉は黒く油がのったような色合いですが、茶湯は鮮やかな赤色(紅)を呈し、葉底(茶殻)も赤くなります。長く続く甘い花や果実のような香りと、渋みが少なくまろやかな味わいが特徴です。
- 代表銘柄: 祁門紅茶(きもんこうちゃ)、雲南省の滇紅(てんこう)、金駿眉(きんしゅんび)。
6. 黒茶(くろちゃ / Dark Tea):微生物の力が生む熟成美

Geminiにより生成
発酵度:後発酵
中国語の「黒茶」(Hēi Chá)は、英語の「Dark Tea」(ダークティー)に相当します。製造過程で微生物の力を借りた「積み上げ発酵」(渥堆、Wòduī)を経るのが最大の特徴です。茶葉の塊自体もとても黒く、私も初めて見た際は炭かと思うほどでした。
- 製造のポイント: 殺青、揉捻、乾燥の後、茶葉を積み重ねて湿らせ、微生物による発酵(後発酵)を促します。この工程は、茶葉を柔らかくし、独特の風味を生み出します。輸送の利便性から、多くが磚茶(たんちゃ/レンガ状)や沱茶(だちゃ/お椀状)などの緊圧茶に加工されます。
- 特徴: 乾いた茶葉は黒く潤いがあり、茶湯は澄んだ琥珀色や橙色を呈します。香りはまろやかで、滋味は濃く熟成した風味があり、後に甘みが残ります。
- 代表銘柄: 普洱茶(プーアルちゃ)、湖南省の安化黒茶(あんかこくちゃ)、広西の六堡茶(ろっぽうちゃ)。
発酵度でわかる味と香りの違い
- 発酵が浅い(緑茶・白茶) → 清涼感・爽やか・渋みあり
- 中程度(青茶) → 花香・果香・バランスが良い
- 発酵が深い(紅茶・黒茶) → 甘み・まろやかさ・熟成感
発酵度を知ることで、味の傾向を予想できるようになります。
例えば「今日は爽やかにいきたい」なら緑茶、「落ち着きたい」なら黒茶、といった選び方も楽しいです。
中国茶の世界を楽しむために
中国の六大茶類は、それぞれ異なる加工技術と発酵度が、茶葉に無限の可能性をもたらします。
この分類を知ることで、「このお茶は発酵度が低いからフレッシュなはずだ」「このお茶は後発酵だから熟成したまろやかさがあるはずだ」といった予想ができるようになり、中国茶のテイスティングが格段に面白くなります。
次は、あなたの好みのお茶を見つけるために実際に六大茶類の飲み比べに挑戦してみてはいかがでしょうか?